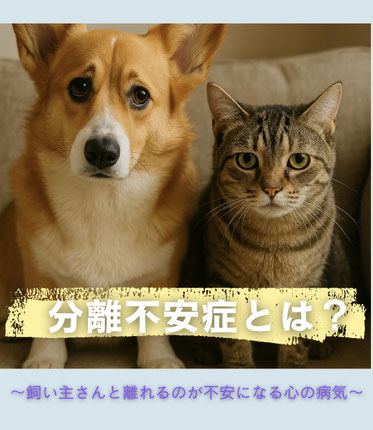
犬や猫が、飼い主さんと離れるときに強い不安を感じてしまう状態を「分離不安症」といいます。
飼い主さんが出かける準備を始めるとソワソワしたり、外出中に吠え続ける、部屋を荒らすといった行動が見られることがあります。
🧠 分離不安症の主な症状
分離不安症の症状は、犬と猫で共通するものも多くあります。
犬の場合
-
お留守番中に吠え続ける、ドアや家具を壊す
-
飼い主が出かけるときに強い不安を示す(鳴く、震える)
-
食欲がなくなる、下痢や嘔吐を起こす
-
飼い主が帰宅すると過剰に興奮して甘える
猫の場合
-
飼い主がいないと鳴き続ける
-
トイレ以外の場所で排泄する
-
食事をとらなくなる
-
毛をむしる(過剰なグルーミング)
このような行動は、叱っても改善せず、かえって不安を強めてしまうことがあります。
💡 なぜ分離不安症になるのか?
分離不安症の原因はひとつではありませんが、主に次のようなことが関係しています。
-
飼い主との結びつきが非常に強い(依存傾向)
-
子犬・子猫の時期に長時間ひとりで過ごす経験が少なかった
-
引っ越しや家族構成の変化など環境のストレス
-
飼い主が急に長時間外出するようになった
犬では特に「常に飼い主のそばにいる」ことが習慣化すると、離れる時間への耐性がつきにくくなります。
🩺 診断と治療
分離不安症は、行動や生活環境をよく観察して診断します。
他の疾患(ホルモン異常や神経疾患)との区別も大切です。
治療は、主に「環境調整」と「行動療法」を中心に行います。
環境調整のポイント
-
外出時のサイン(カギを持つ・靴を履くなど)を日常的に行い、出かける=不安の合図にならないようにする
-
出かける前にたっぷり遊んで、満足感を与える
-
飼い主が不在のときに、好きなおもちゃやおやつを与える
-
飼い主の外出や帰宅時は大げさに構わないようにする
行動療法と併用
-
徐々に留守番の時間を延ばして慣らしていく
-
獣医師の指導のもと、必要に応じて抗不安薬などの投与を検討
焦らず、少しずつ「ひとりでも安心できる時間」を増やすことが重要です。
🏡 飼い主さんにできるサポート
-
外出時に声をかけすぎない
-
帰宅後もすぐに抱きしめず、落ち着いてからコミュニケーションをとる
-
生活リズムを一定に保つ
-
適度な運動とスキンシップを毎日行う
分離不安症は「わがまま」や「しつけ不足」ではなく、
ペットが感じている「不安のサイン」です。
叱るのではなく、安心できる環境を整えてあげましょう。
💬 飼い主さまへのメッセージ
分離不安症は、時間をかければ改善することができる行動の問題です。
飼い主さんとペットの関係性を見直し、少しずつ「離れても大丈夫」という安心感を育てていくことが大切です。不安の症状が強い場合は、ご相談ください。
🔬 獣医外科認定医(JAHA)/獣医腫瘍科認定医在籍
整形外科・腫瘍科・歯科・皮膚科などの専門診療にも対応しています。
📞 ご予約・お問い合わせはこちら
📍365日診療のガレン動物病院
平日・土日・祝日すべて診療しております。
急な体調の変化も、予防・健康診断も、お気軽にご相談ください。
ネット予約 ▶︎ https://pet.apokul.jp/web/390/reservations/add
電話 ▶︎ 055-972-6770
🚗 対応エリアのご案内
ガレン動物病院には、三島市・沼津市・函南町・長泉町・裾野市・伊豆市・御殿場市・富士市・静岡市・箱根町など、
静岡県東部・神奈川県西部エリアからも多くの飼い主さまにご来院いただいています。














